刀ミュ『坂龍飛騰』は、観終えたあと、言葉を探すのに時間がかかる――そんな深い余韻を残す作品でした。
陸奥守吉行という一振りを主軸に、歴史を守るという名の非情な任務、そして“物部”という存在にまつわる謎と葛藤が描かれます。
多くのファンの間で賛否が分かれるこの作品には、さまざまな読み解き方があります。
本記事では、ネタバレ感想を含みながら、物語を深く掘り下げた“考察”としてまとめました。
なぜこの作品が賛否を呼んでいるのか?
物部とは一体何者だったのか?
そして、陸奥守吉行が流した涙の意味とは何だったのか?
その問いの先に、この作品が描こうとしたものが見えてきます。
納得はできなくても、心に残る。そんな作品に出会ってしまった方へ――その感情の行き先を、ここで一緒に探っていきましょう。
坂本龍馬を何度も殺した佩刀――陸奥守吉行の業
陸奥守吉行が、感情を捨てたような顔で坂本龍馬を暗殺していく——。
幕が上がってすぐのそのシーンは、まさに観客の心を一気に掴む衝撃的な幕開けでした。
「坂本龍馬の佩刀」として知られる陸奥守吉行が、自らその主を斬る。
それも任務として、歴史を守るために幾度も、何度も。
驚きだったのは、それが陸奥守自身の意志だったということです。
時間遡行軍が坂本龍馬を守ろうとするたびに、刀剣男士たちは“歴史通りに”龍馬を死なせなければなりません。
そんな状況で、陸奥守吉行は自ら進んで「龍馬の任務に自分を加えてほしい」と申し出ていたのです。
誰かがやらなければならないなら、自分がその手で終わらせる。
それが、坂本龍馬の佩刀である自分の役目だと考えていたのでしょう。
坂本龍馬の佩刀として、その死を、命を、最後まで見届けるのは自分であるべきだと。
けれどそれは、あまりにも重い業でした。
「ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ、押し寄せる波の数」と歌いながら、彼はいったい何度、坂本龍馬を殺してきたのでしょうか。
脱藩から暗殺までの龍馬が歴史の表舞台に立った約7年を優に超える数、くり返してきたのだと思います。
やがて感情は磨耗し、龍馬の記憶も薄れていき、「龍馬の死」はただの作業になってしまっていたのかもしれません。
しかし、今作では違いました。
“リョウマ”と名乗る男――坂本龍馬の代わりにその名を生きた存在の死を見届けたとき、陸奥守吉行は涙を流します。
あの涙には、悲しみと、祈りと、救いが込められていたように感じました。
ようやく、失っていたものを取り戻したように見えました。
これからも彼は、何度も坂本龍馬を死なせる任務に就くのだろうと思います。
けれどその中で、「陸奥守吉行のために坂本龍馬として生き切った誰か」が確かにいた。
陸奥守吉行の心に、それは確かに寄り添っていると感じました。
理不尽さも、虚しさも、やるせなさもすべて抱えながら、それでも前を向こうとする一振り。
審神者として、彼がほんの少しでも救われてほしいと願っています。
物部という存在に感じた疑問と希望
――陸奥守吉行が涙を流した理由は、単なる代役としての“坂本龍馬の死”ではなかった。
その名を背負って生き切った、リョウマという“ひとりの命”に心を動かされたからだと思います。
ここでは、もうひとつの主題である「物部という存在」について触れておきたいと思います。
坂本龍馬を殺し続けてきた陸奥守吉行。
そんな彼の前に現れたのが、“物部”という存在でした。
今作のリョウマ——彼の正体が明らかになったのは、千秋楽公演後の公式キャスト更新。
「リョウマ・坂本龍馬」という名前を見た瞬間、胸の中に複雑な感情が込み上げました。
初日配信を見た感想レポで自分は物部の存在に理不尽さを感じ、「物部の彼の本当の名前すら知らない」と嘆きましたが物部の彼の名が「リョウマ」だと知って天を仰ぎました。
「俺はリョウマだよ」
彼がそう口にした時、それは坂本龍馬を名乗るという意味ではなく、“本当の名前”だったと、その可能性すら考えていなかったことに打ちのめされた気持ちでした。
彼を「物部」、「坂本龍馬の代役」と考えていたのは誰よりも自分だった。
刀ミュにおける「物部」とは、三日月宗近が過去から救い上げた、“本来の歴史では死ぬはずだった人々”の集まりです。
『つわものどもがゆめのあと』では源義経を、『三百年の子守唄』では徳川信康を逃がし、生かしてきました。
「死んだはずの人物が、実は生き延びていた」という所説の可能性に光を当てた存在です。
けれど、今回のリョウマは違いました。
火事で死ぬはずだった幼い百姓の子。
それが三日月宗近によって助けられ、生き延びた彼には“所説が存在しない”のです。
歴史に大きな影響を与える人物ではない、ただの百姓の子ども。
だからこそ助けられ、「静かに生きる」よう告げられた。
けれど、その子は一人寂しく生きることを拒絶してしまった。
それはそうだ。
歴史の修正力も何も知らない幼い子に一人で生きろというのはさすがに酷でしょう。
三日月はちょっとその辺の機微が疎すぎる気がする。神様視点が過ぎるというのかな?
けれどそのせいで、ただ生きろと願われたはずの命が、やがて坂本龍馬に瓜二つの姿となって“龍馬の代わり”として戦場に立たされるようになってしまったのです。
本来、命を懸ける武士でもなく、ただの百姓だった名もなき彼が、「腐り落ちる花にはなりたくない」と願い、坂本龍馬として生き切って死ぬことを選んだ。
これは、彼自身が選んだ“死に花”だったのでしょうか。
……そう思いたいです。
けれど、その決断が本人の自由意思だけによるものだったのかは分かりません。
押し寄せる期待や歴史の重圧が、彼を追い詰めていなかったとは言えない。
死に追いやられてしまったようにも感じてしまうから、どうしても胸が痛むのです。
三日月宗近は、なぜ彼を助けたのでしょうか。
火事から救ったあのとき、こんな未来を想像していたでしょうか。
「静かに生きろ」と願った命が、歴史に名を刻まぬまま「坂本龍馬の代わりとして死ぬ」ことになる。
それを“救い”と言っていいのか――今も、はっきりと答えは出せません。
けれど一方で、リョウマは「侍のいない世の中」を願っていました。
重い年貢に苦しみ、「侍をなくしてくれ」と神に願うほどだった彼。
坂本龍馬が実現した「大政奉還」、侍の時代を終わらせたという偉業。
その人生を生ききったことで、彼は自分の願いを叶えたのかもしれません。
坂本龍馬の死に、陸奥守吉行が涙を流すことはなくなってしまった。
でも、リョウマという、歴史にも記録されない名もなき命が「坂本龍馬」として生き切ったことで、
彼の心に何かが灯った。
それは、この物語が描いた“唯一の希望”だったのかもしれません。
肥前忠弘という“人間らしさ”と葛藤
今作で、もう一つ心に強く残ったのが――肥前忠弘の描かれ方でした。
正直、納得がいかない。
感情としては、かなり引っかかってしまいました。
坂本龍馬に強い思い入れを持つ肥前忠弘は、リョウマが“坂本龍馬の代役”として立たされることに耐えられなかった。
その結果、部隊から離脱してしまいます。
歴史を守るという任務は、刀剣男士にとって何よりも優先すべき使命。
それを放棄したように見える彼の行動は、刀としてどうなんだろう?と疑問を感じたのが正直なところです。
ですが、それと同時に、彼の“人間らしさ”にも心を動かされてもいました。
坂本龍馬を本当に大事に思っていたからこそ、リョウマという存在をどうしても受け入れられなかった。
あの、泣きそうな、でも泣きたくなくて睨むような目を向けた表情には、どうしようもない苦しさがにじんでいたように思います。
また、離脱してしまうことで物理的に舞台上での出番が減ってしまったのは、ファンとしては本当に寂しかったです。
陸奥守吉行との関係性も、リョウマとの関わりも深いキャラクターだったからこそ、もっと見ていたかったという気持ちは拭えません。
それに、刀としての肥前忠弘の扱いにも思うところがありました。
史実では、坂本龍馬が脱藩する際に家族から託された大切な刀であり、のちに岡田以蔵へと譲られたという経緯があります。
そんな大事な刀が、今作では――あまりにもあっさりとリョウマの手に渡されてしまいました。
泣き崩れる岡田以蔵に、リョウマがまるで「代わりに」とでも言うように手渡した肥前忠弘。
あの描写には、やっぱりモヤッとせざるを得ませんでした。
もちろん、リョウマには肥前忠弘への思い入れがない。
それは当然のことかもしれません。
でも、だからこそ、あの渡し方は少し残酷にも見えました。
坂本家の家宝だった陸奥守吉行。
その「もうひと振り」とも言える肥前忠弘。
土佐組の一員として、岡田以蔵、南海太郎朝尊との“絆”が今作にも流れていたことを思えば、肥前忠弘にも、そして南海太郎朝尊にも、もっとスポットライトが当たってほしかった。
本音を言えば、もっと彼らの心情を見せてほしかった。
歴史通りに死んでいった岡田以蔵と武市半平太。
それを見届けてきた肥前忠弘と南海太郎朝尊。
特に肥前忠弘は、「江水散花雪」に続き元の主との関わり方に救いがない。
救いがないからこそ、「いつかは」と思ってしまう。
それが“極”という形かもしれない。 そう考えることで、少しだけでも希望を持っていたいと思いました。
坂龍飛騰が伝えたかったものは何か
『坂龍飛騰』を観終わって、最も強く感じたのは――
「これは、陸奥守吉行のための物語だった」という思いです。
坂本龍馬を何度も殺さなければならなかった任務の日々。
彼の心がどれほど擦り切れていたかは、劇中での無表情や乾いた笑みに表れていました。
そんな彼が、物部=リョウマの死に涙を流した。
その姿に、私は少し救われたような気がしました。
何度も龍馬の死を経験し、悲しみすら持てなくなっていた彼が、再び“涙”を流すことができた。
それは、あまりにも当たり前で、それでもとても尊い感情でした。
もちろん、「物部」という存在に対する疑問や違和感は、今も残っています。
結果としてただ歴史を補うために生まれ、誰かの代わりとして死ぬ。
与えられた役割を演じるために存在したような彼の姿は、どこか痛ましく、そしてやるせなさが残ります。
けれども、彼は“坂本龍馬として散る花”であることを選びました。
刀剣男士たちもまた、与えられた使命の中で葛藤しながら、それでも人の想いを大事にしてきた存在です。
坂本龍馬という“散る花”への愛を、再び思い出すことができた――それが陸奥守吉行にとって、何よりの救いだったのではないでしょうか。
そして、陸奥守の龍馬への愛を思い出す“きっかけ”を与えたのが三日月宗近でした。
陸奥守吉行は三日月宗近に対して怒りを見せていました。
個人的には陸奥一蓮やパライソで鶴丸国永が三日月宗近に向けた怒りにそっくりで驚いたほどです。
陸奥守は鶴丸や山姥切国広に並ぶ最古参なんだなと自然と納得してしまいました。
陸奥守は「天から降りてこい」と月に向かって号砲を撃ち鳴らしていました。
まるで神様のように歴史上で救われなかった人間たちや刀剣男士を救おうとする三日月宗近に向けた、痛切な叫びでした。
この物語は、三日月宗近が“陸奥守吉行のための救い”として作り上げた物語なのだと思います。
“散る花”に込められた美学と、刀剣男士の愛
『坂龍飛騰』では、“散る花”というモチーフが何度も登場していました。
花は咲いて、やがて散る。
それは自然の摂理であり、美しさと儚さの象徴でもあります。
ですが今作では、その散り際の美しさに、残酷さが重なるようにも感じられました。
なかでも印象的だったのが、肥前忠弘のこの台詞です。
「散るべき時に散れなかった花は腐るだけだ。俺に摘ませるなよ」
この言葉には、潔さと諦念、そして命に対する深い感情が込められていたように思います。
散るべき命は、潔く咲き誇って終えるべきだ――
それはまさに刀剣男士たちが日々向き合っている“歴史”そのものでもありました。
武士にとっては死に花ともいうでしょうが、生き様に関しては武士に限らないと思っています。
そしてこのセリフは、坂本龍馬という存在への、そしてリョウマという命への「愛」でもあったのだと思います。
リョウマは、坂本龍馬という“散る花”を演じきった。
本来であれば生き延びるはずだった命が、代役という宿命を背負い、「死を選んで咲ききった」ことに、肥前忠弘は複雑な感情を抱いていたのかもしれません。
一方で、かつて『江水散花雪』で和泉守兼定が言ったこの言葉を思い出しました。
「咲き誇ろうが朽ち果てようが、俺は俺の花を愛でる」
命の長さや役割に関係なく、そこに咲いた命を愛する。
それは刀剣男士にとっての優しさであり、誇りであり、願いでもあるのでしょう。
それを踏まえて考えるなら、
リョウマが「坂本龍馬として咲き、散る花」になったこと。
そして、それを見届けた陸奥守吉行が涙を流したこと。
その瞬間に込められた感情の深さこそ、今作の核だったのかもしれません。
たとえ終わりが見えていても、そこに咲いた命をちゃんと見つめ、愛でて、そして見送る。
それが、刀剣男士たちにできる最大限の“愛”なのだと感じました。
なお、二部のライブパートの感想については、別記事でネタバレなしのレポートとしてまとめています。
セトリや演出の印象などを知りたい方は、ぜひこちらもあわせてご覧ください。
👉 ミュージカル『刀剣乱舞』坂龍飛騰 ライブパート感想(ネタバレなし)
あなたにも、この物語を見届けてほしい
『坂龍飛騰』には、さまざまな意見があると思います。
物部という存在の意味。
リョウマの扱い。
肥前忠弘の出番や心情の描かれ方。
どれも簡単に割り切れるものではなく、モヤモヤした気持ちが残る部分も多かったです。
正直、観終わってからも気持ちの整理には少し時間がかかりました。
けれど、その曖昧さや苦しさも含めて、私はこの作品が「陸奥守吉行という刀の物語」として必要なものだったと感じています。
だからこそ、陸奥守吉行が好きな方にはぜひ観てほしいです。
彼がどんな役割を背負い、何を思い、そしてどんな“救い”を得たのか――その姿を見届けてほしい。
また、土佐組(陸奥守吉行・肥前忠弘・南海太郎朝尊)推しの方にとっても見どころの多い舞台です。
三振りの関係性、積み重ねた歴史、そしてそれぞれの“選択”と“生き方”。
胸が締めつけられるような場面も多いですが、それだけに深く愛おしさをを感じられる瞬間もたくさんあります。
納得できない部分があったとしても、受け取り方は人それぞれ。
自分の気持ちを大切にしながら、他の人の感じ方にも耳を傾けられたら――
それが、この作品と向き合ううえで大切な姿勢なんじゃないかなと思います。
そしてもし、これからこの作品を観ようか迷っている方がいるなら――
どうか、一度観てみてください。
ただの歴史改変モノじゃない。
ただのバトルものでもない。
その奥には、「刀剣男士が命にどう向き合うのか」という、とても人間くさいテーマが息づいています。
最後まで観たあと、きっと何かが心に残るはずです。
まとめ:痛みと救いを抱えた陸奥守吉行の“いっとうかっこええ”物語
『坂龍飛騰』は、爽快感で終わる作品ではありませんでした。
けれどその代わりに、観た人の心に“どうしようもない痛み”と、それでも“かすかな救い”を残していった物語だったと思います。
歴史を守るためとはいえ、坂本龍馬の死を何度も見届け、あるいは自らの手で命を奪ってきた陸奥守吉行。
あまりに非情な任務の中で、感情すらすり減らし、悲しむこともできなくなっていた彼が、物部=リョウマの生き様を通して、ようやく「坂本龍馬の死」を悲しむことができた。
それは、彼にとってほんの一瞬の、けれど確かな“癒し”であり“救い”だったように思います。
物部の存在や、その役割については、今もなお賛否が分かれるでしょう。
自分自身、納得しきれない部分がなかったとは言いません。
けれど、それでもこの物語を通して、陸奥守吉行が「坂本龍馬を愛する一振り」として確かに“報われた”瞬間があった。
その姿が、涙を流すその横顔が――
まさに「いっとうかっこええ坂本龍馬の佩刀」だったと思います。
誰かの命に向き合い、歴史の重みを受け止めること。
それを背負ってなお、生き続ける刀剣男士の強さと優しさ。
『坂龍飛騰』は、そんな彼らの“生き様”を静かに、けれど力強く描いた作品でした。
……というわけで、本編についての感想はここまでです。
ちなみに、二部のライブパートの様子については、ネタバレなしの感想記事にありますので、よかったらそちらもどうぞ。
👉 ライブパート感想(ネタバレなし)はこちら
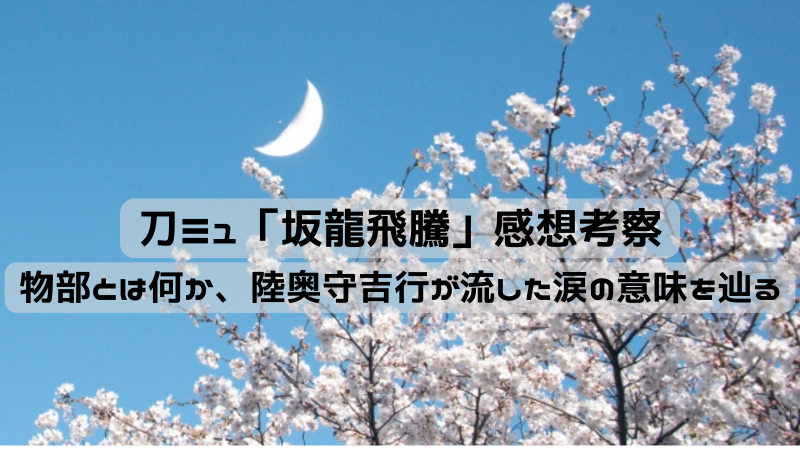


コメント